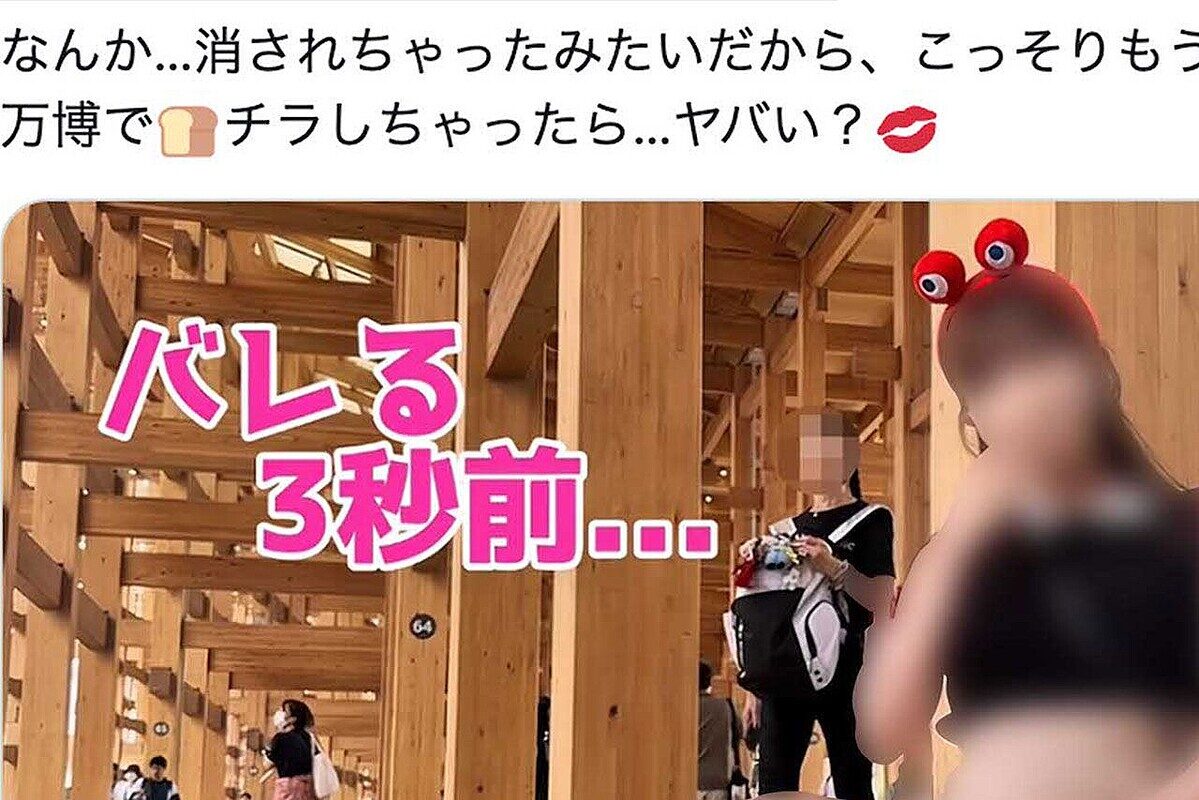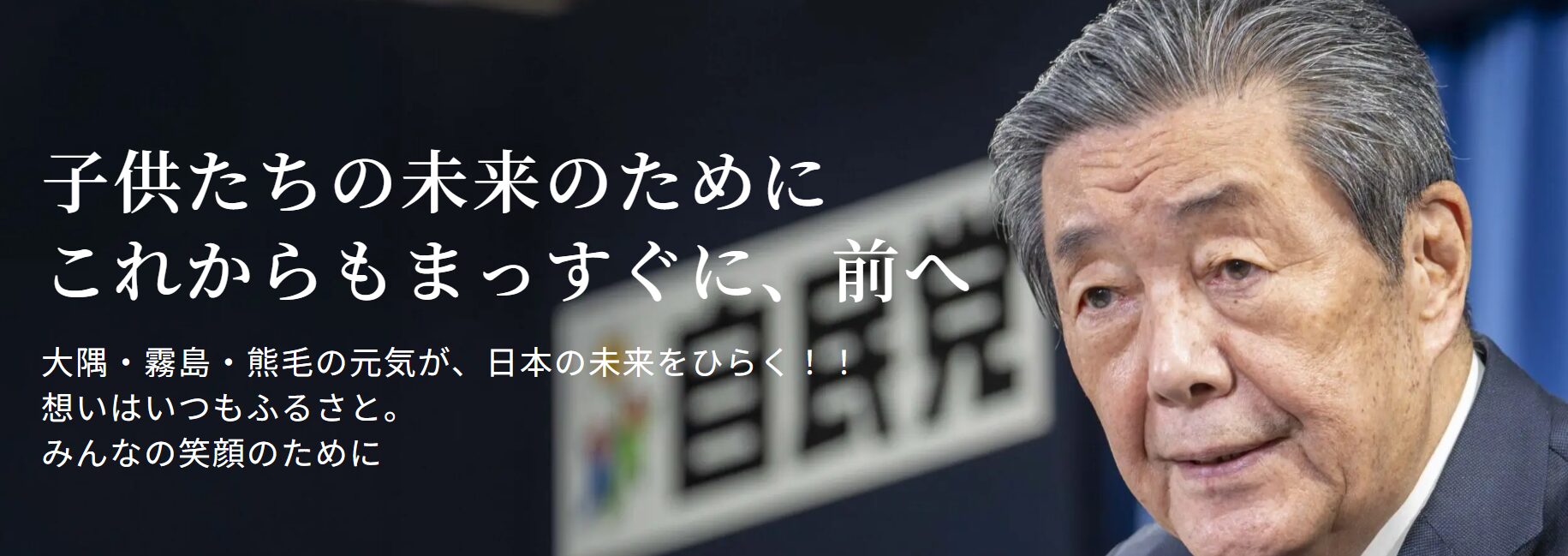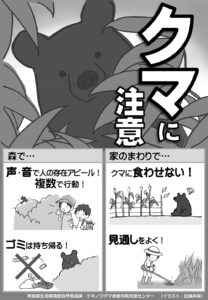【ガリガリ君の家族構成】ガリガリ君、家族が増える。名前は?弟か妹か、それともペット?
【ガリガリ君の家族構成】ガリガリ君、家族が増える。名前は?弟か妹か、それともペット?ガリガリ君に家族が増えるそうです。 家族予想キャンペーンを実施中で、応募者の中から抽選で10名に保冷...

JAが米の価格操作を行っているという指摘は、在庫調整と流通支配による市場価格への影響力に基づくものです。
実際、JAは市場シェア5割を占める独占事業体として、在庫量を調整して市場への流通量をコントロールすることで、相対価格を高く維持しているとされています。
「JAを通すとコメ価格が上がる」にJA福井県が異議 5キロ2000円台の“格安備蓄米”には「適正価格は3600円程度」(Yahoo!ニュース)
JAは本当に米の価格操作をしているの?その仕組みと実態を解説

JAが価格操作を行っているという指摘の根拠は、その圧倒的な市場支配力にあります。
JAグループは米市場において5割のシェアを占める独占事業体として機能しており、在庫量を調整することで市場への流通量をコントロールしているとされています。
これは一般的な市場原理とは異なる仕組みです。
卸売業者は相対価格をベースに自らのマージンを加えてスーパーや小売店に販売するため、相対価格が下がらなければ小売価格も下がらないという構造になっています。
この相対価格をコントロールできるのがJAなのです。
また、備蓄米放出の入札でも21万トンのうち9割以上をJAグループが落札しているという事実も、JAの影響力の大きさを物語っています。
つまり、JAは生産から流通まで一貫して関与することで、実質的に米価格をコントロールする力を持っていると考えられるのです。
なぜJAは米の価格を左右できるのか?
JAが価格を左右できるのは、米流通における圧倒的なシェアと在庫調整機能を持っているからなのです。
JAが米価格に大きな影響力を持つ理由は、日本の米流通システムにおける特殊な地位にあります。
戦後から続く農業政策の中で、JAは農家の生産支援から販売まで一手に担う組織として発展してきました。
現在でも多くの農家がJAを通じて米を出荷しており、この集約力が価格への影響力の源泉となっています。
JAは在庫調整を手段として利用することで米価を操作してきたとされています。
つまり、豊作の年には在庫を増やして市場への供給を抑制し、逆に不作の年には在庫を放出することで価格の安定化を図るという機能を担っているのです。
しかし、この機能が時として価格の高止まりを招く要因にもなっていると指摘されています。
さらにJAの持つ組織票は政治に影響を及ぼすほどの力を持っており、農業政策の決定過程においても無視できない発言力を有しています。
このような背景から、単なる経済団体を超えた存在として、米価格に対する影響力を維持していると考えられます。
米価格を完全にコントロールするJAの流通システムとは?
JAの流通システムは生産から小売まで一貫したルートを形成し、相場に大きな影響を与えています。
JAの流通システムが価格操作の温床とされる理由は、その垂直統合的な構造にあります。
農家から米を買い取り、保管・精米を行い、卸売業者を通じて小売店に販売するまでの全工程をJAグループが管理しているのです。
この一貫したシステムにより、各段階での価格決定に関与することが可能になっています。
特に問題視されているのは、JAが在庫量を調整して市場への流通量をコントロールすることで、相対価格を高く維持している点です。
例えば、豊作で本来なら価格が下がるはずの年でも、JAが在庫として保有することで市場への供給量を制限し、価格の下落を防ぐことができます。
これは農家の収入安定には寄与しますが、消費者にとっては高い米価格が続く要因となります。
また、JAグループの山野徹会長は「コスト増加分を販売価格へ反映していかなければ持続可能な生産は実現できない」と述べており、価格維持への意図を示唆しています。
コメ高騰で「消費離れ」懸念 JA全中の山野会長(時事ドットコム)
このような発言からも、JAが積極的に価格水準の維持を図っていると考えられます。
JAによる備蓄米買い占めはなぜ起きたのか
米価高騰への対応として政府が備蓄米の放出を決定した際、入札には主にJA全農や各地のJA、集荷業者が参加しました。
JA全農が初回放出分14万1796トンのうち9割超にあたる13万2999トンを落札した背景には、いくつかの理由があります。
JA全農が大部分を落札した理由
- 発達した流通網: JA全農は全国的な流通ネットワークを持っており、大量の米を捌ける体制が整っている
- 価格競争力: 資金力があり、入札において高い価格を提示できた
- 取扱能力: 14万トンという大量の備蓄米を保管・処理・流通させる能力がある
ただし、この集中的な落札については批判的な見方もあります。
備蓄米が消費者に届くまでの流通過程で価格が十分に下がらないという問題が指摘されており、「JAに放出すべきでなかった」という声も多く上がっています。
政府は米価高騰対策と称して備蓄米を放出したものの、実際にはJAが入札した段階ですでに高値であり、価格を下げる効果はまったくありませんでした。
これには組織票を持っているJAへの忖度があったとも言われています。
米価が下がらないのはなぜ?JAによる価格操作の噂を検証
米価が下がらない主要因の一つとして、JAの在庫調整と流通支配が影響していることは事実です。
近年の米価高騰について、政府は様々な理由を挙げていますが、専門家の間ではJAの役割に注目が集まっています。
農林水産省は新米が供給されれば価格は落ち着くと主張していますが、実際には値段は一向に下がっていません。この現象の背景には、JAの戦略的な在庫管理があると考えられています。
農水省はJA農協以外の流通ルートが増えたから米価が上昇していると説明していますが、「これは全くの虚偽であり米価を高く操作してきたのはJA農協そのもの」という厳しい指摘もあります。
つまり政府の説明とは異なり、JAこそが価格高騰の主因だというのです。
実際に、備蓄米の放出でも9割以上をJAが落札しているという事実があります。
そしてこれは、政府が価格抑制のために行った施策でさえ結果的にJAの影響下に置かれていることを示しています。
このような状況では市場競争が機能せず、消費者が適正価格の恩恵を受けることが困難になっているのが現実なのです。
農業協同組合の本来の役割と現在の問題点とは?
JAの米価格への影響は、農家保護という名目の下で消費者の負担増大を招いている構造的問題です。
JAと米価格操作の関係を理解するには、戦後の農業政策の変遷を知る必要があります。
JAは元々、小規模農家の利益を守るために設立された協同組合でした。
しかし、時代の変化とともにその機能は農家保護から組織維持へとシフトしていると指摘されています。
現在の問題点として、JAは独占事業体として在庫量を調整し、市場への流通量をコントロールすることで相対価格を高く維持していることが挙げられます。
この仕組みにより、本来なら市場原理によって決まるべき価格が人工的に高く保たれているのです。
結果として、消費者は必要以上に高い価格で米を購入することを余儀なくされています。
また、JAグループは自民党と深いつながりを持つとされ、政治的な影響力も価格政策に反映されていると考えられます。
このような政治との癒着構造が、抜本的な制度改革を困難にしていると言われています。
真の消費者利益を実現するには、JAの役割や必要性の見直しと、より透明で競争的な米流通システムの構築が求められているのが現状なのです。
ついに米の流通にメスを入れた小泉進次郎新農林水産大臣。
JAの巨大な組織票に揺らぐこと無く突き進む小泉進次郎氏の改革に、コメ価格高騰に苦しんでいる国民から熱い注目が集まっています。
ややこしい?JAと農協と全農と全中の違いを解説
日本の農業協同組合系統は階層構造になっていて、それぞれ異なる役割を持っています。
JA(農協)
正式名称は「農業協同組合」で、地域の農家が集まって作った協同組合です。
各市町村や地域ごとにあり、農家への営農指導、農産物の販売、資材の供給、貯金や融資などの金融サービスを提供しています。
全国に約600のJAがあります。
全農(JA全農)
都道府県レベルや全国レベルでJAをまとめる経済事業の中央組織です。
正式名称は「全国農業協同組合連合会」で、各JAから農産物を集めて大口販売したり、肥料や農薬などを大量購入してJAに供給したりします。
農産物の流通や販売で大きな力を持っています。
全中(JA全中)
「全国農業協同組合中央会」の略で、JA系統全体の指導・監査を行う組織です。
政策提言、教育研修、監査業務などを通じてJA系統全体をまとめる役割を担っています。
JAとは?まとめ
簡単に言えば、JA(現場)→ 全農(流通・販売)→ 全中(指導・統括)という関係で、作物が生産者(農家)から消費者に届くまでを管理してとりまとめる組織体系になっているのです。
全てをひっくるめて呼ぶなら「JA」となります。